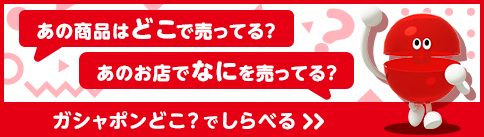第1回 渋谷浩康プロデューサー談

ULTRA N PROJECT、始動!
――まずは「ULTRA N PROJECT」という一大プロジェクトの成り立ちを改めて語っていただけますか。
当時は「ULTRAMAN THE NEXT」と呼ばれていましたが、のちの映画『ULTRAMAN』が企画的には先行していまして、同時期に始まるであろうテレビシリーズのほうもブランディングを受け継ぐだけでなく、世界観的にも連動が出来る作品にしていこうという考えがありました。
――前作『ウルトラマンコスモス』も、よく似た構造でしたよね。テレビシリーズの放送開始から間を置かずして、その前日譚である劇場版が公開されるという。
ええ。でも『ULTRAMAN』に関しては、より一般的な映画のような展開が目指されており、その公開時期も冬季での調整となりました。そうなるとテレビシリーズのほうがだいぶ先行することになります。まず映画があって、“今度のウルトラマンシリーズはこういう感じでやっていくんだよ”ということを打ち出してからではなく、連動を明かさずに徐々に『ULTRAMAN』の世界観に近づけていかなければならない。それに『コスモス』が終わってから2年くらい経っていたので、テレビシリーズと映画への橋渡しとしてのライブイベントや児童誌グラビア展開による事前の盛り上がりも必要な要素でした。そこでネクストが地球にやってくる前の姿であるキャラクターが、正体を明かさずに歴代のウルトラマンたちと共闘するプレパブリシティを展開しました。当初は「スペースネクスト」と呼んでいましたが、これがウルトラマンノアによる展開『バトルオブドリーム ノア』ですね。ということで、ノア・ネクサス・ネクストが揃いました。
――『ウルトラマンネクサス』は10月放送開始、『ULTRAMAN』は12月公開でしたが、確かにノアのお披露目はもっと早かったですね。
当時、ノアには春からの児童誌グラビア連載で活躍してもらい、夏の「ウルトラマンフェスティバル」との連動による盛り上がりを経て、テレビシリーズのパブリシティへと続く流れを作っていきました。イベント、テレビ、映画へと手を替え品を替え、ランクアップさせつつ、最後に連動を明かしてみんなに楽しんでもらおうと思っていたんです。
――『ULTRAMAN』には製作協力プロデューサーとしてクレジットされていますが、ノア周りの展開にも深く関わられていたんでしょうか?
そうですね。ノアの設定を作成し、連動展開案を企画立案しました。たとえば児童誌のグラビア連載だったら、この号はこういう活躍をして、この号でダークザギが出てきて、最後はウルトラマンフェスティバルのライブステージとも連動するといった連動展開の構成案を作成したりしていましたね。
――現在では、ザ・ネクストとネクサスとノアは同一キャラクターということが広く知られていますが、当時は伏せられた情報でしたよね。
謎解きというかサプライズというか、ひとつひとつ別のキャラクターなんだろうなと思って見ていたものが繋がっていく面白さをプレゼントしたい!というのが、プロデュース側の想いでしたね。
――『ULTRAMAN』側のチーフプロデューサーは、鈴木清さんでした。
当時の円谷プロはテレビ班と映画班が別班で動いていたのですが、僕は元々、鈴木プロデューサーの映画班でアシスタントプロデューサーを務めており、鈴木さんのもとで鍛えられていたんですよ。これが何でもやる仕事で、企画・脚本開発から撮影に仕上げ、そして宣伝、劇場公開といった流れを一連で経験することができたんですね。たとえば『ティガ&ダイナ(ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち)』であれば、テレビと映画でスーツアクターさんをどう分けるかとか、セットやミニチュアの調整とか。テレビシリーズの撮影の合間を縫って映画のパブリシティやイベントに出演してもらうために、つるの(剛士)さんたちのスケジュール調整をしたり、隊員服や装具一式を借りてきて、きちんと管理してまたテレビ班に返却したり……そんなふうにものすごく骨を折ることも多かったんですけど、プロデューサーになったとき、映画班の状況もテレビ班の状況もよく分かったし、協賛企業の方々や社内の各セクションとも話がしやすかったんですよ。それこそバンダイさんともAP時代からのお付き合いがありましたから。アイテム連動のやり取りなどは、若手の担当同士にまかせてもらえて、細かいところを詰めていくようなスタイルだったんです。そういう経験を積んでいたので、『ネクサス』では連動要素でサプライズを作りつつ、バンダイさんとのマーチャンダイジングも数多く展開出来たんじゃないかなと思いますね。要は調整役も重要なんですよ。
――そもそも『ネクサス』って、非常に攻めた企画だったと思うんですが、周囲からの反対意見はなかったんですか?
「こんなに素晴らしい作品なので、このまま何を言わずにやらせてください!」みたいな感じで振る舞っていたら、「ちょっと自分は乗れないなぁ」って方も出てきたと思うんですけど、相手の立場に沿うかたちで物事を進めていくことで、ストーリーファーストな部分はストーリーファーストで構わないという合意を得ることができたというか、こだわりたい部分にはこだわることができました。
――なるほど。「絆」というテーマは、どういうきっかけで生まれたものなんですか?
もちろん、テーマが明確でなくても現場は回るのですが、プロデューサー的には「今回はこういうテーマでいきます!」っていう大きな旗印が必要なんですよ。テーマはスタッフとキャスト、そして視聴者をつなぐ、シリーズを通したメッセージになりますので。たとえば『コスモス』では「慈愛」でしたが、のちの『ネクサス』以上の反発が当初はありました。やっぱり『ウルトラマンティガ』『ウルトラマンダイナ』『ウルトラマンガイア』とちょっと大人っぽい作品を続けてきてたので、コアな特撮ファンの方々から「せっかく『ガイア』でSFを突き詰めたのに、急にこういう路線ですか?」と。「そもそも怪獣をいいヤツか悪いヤツか見極めるというスタンスは如何なものか?」とかね(笑)。
――基本的にファンというものは保守的ですからね。
でも子供たちが、そういう色眼鏡とか偏見抜きに応援してくれたのがすごく嬉しかった。実際、自分は映画班のAPだったので、舞台挨拶とか握手会で子供たちの姿を見てるんですよ。それこそ『ティガ&ダイナ』だったら、ティガとダイナのソフビを握った子供が、銀幕のティガとダイナの動きに合わせてバク転させてたりする様を目の当たりにして感動したり。だから、彼らよりもう少し上の年齢層に向けて作ってはいたんですけど、そういう子たちが支持してくれているのも実感としてあったので、『コスモス』は子供に向けた優しいヒーローを映画とテレビが連動する企画として提案し、テレビシリーズのプロデューサーになったわけです。で、そんな彼らが『コスモス』の2年後に観るウルトラマンでもあるわけじゃないですか、『ネクサス』は。「ピュアな気持ちを忘れないでね」というのが『コスモス』だとしたら、「世の中には大変なこともあるけれど、それでも頑張ろう! 諦めるな、仲間はいるはずだ」というのが『ネクサス』。つまり身近にいなくても、どこかで繋がっているんだということを「絆」をテーマにした物語を通して教えてあげたい想いがあったんです。
――ハードテイストだからこそ、同時にポジティブなテーマが必要だったんですね。
あと、さっきも言ったように、プロデューサーは様々な人たちと話します。脚本家や監督、スタッフやキャストたちと話します。テレビ局、代理店の人たちとも、バンダイの人たちとも話します……僕は絵が描けるタイプのプロデューサーではないし、ディレクターを兼ねるプロデューサーでもないので、やっぱりロジックや言葉で説明して共感を得ることで企画を成立させていかなければいけない。だから分かりやすい、普遍的なテーマをシチュエーションに当てはめてシリーズを通したメッセージとして描いていくことを、自分のポリシーにしていました。『ネクサス』は、絆というテーマを描いた作品でしたが、作品を作る過程においても様々な絆が生まれた作品でしたね。
――ウルトラマンに変身する人物が移り変わっていく「適能者(デュナミスト)」というギミックもテーマに深く関わってくる要素でしたね。
このテーマだからこのラストに帰結します!というだけでなく、その過程には自分としても様々なことに挑戦したい気持ちがあったので、ミステリー駅伝じゃないですけど、誰がアンカーなのか分からない絆の襷リレーをやってみたいと思いました。もちろん、デュナミストに寄り添い続けていた存在が最後にアンカーになるのは決めているわけですけど、それらの考察が観る人の引きになればいいなと。
――「NEXUS」という単語も、絶妙に耳馴染みのない感じでよかったですね。
本来、絆だったら「BOND」なんですけど、“ウルトラマンバンド”といわれても音楽隊みたいじゃないですか(笑)。それで近しい意味を持つ単語からネクサスと命名しました。まさに言われるとおりで、分かりにくい単語のほうが、あとから気付いて「おおっ!」と思わせる要素になりますしね。名前の印象も重要です。「“名は体を表す”」なので。
――ネクストと響きが似ていたというのも選ばれた理由のひとつだったりするんですか?
いや、それは結果的にそうなっただけで、最初から意識してたことではないんですよ。だって、ウルトラマンバンドになる可能性だってあったくらいですから(笑)。ただ、映画タイトルが『ULTRAMAN』になってもなお、ザ・ネクストがキャラクターの名前として残り、テレビのほうもネクサスという名前になったので、三つ目のキャラクターの頭文字もNがいいだろうとは思いましたね。
ネオスタンダードを求めて
――『ネクサス』といえば、これまでの作品よりも様々な面で規模を縮小せざるを得なかったというファクターが取り沙汰されることも多いわけですが、そこでやろうとしていること自体のスケールは非常に大きかったじゃないですか。ここが面白いところですよね。
無理難題に挑戦するのも円谷イズムですね(笑)。バジェットをコンパクトに、スケジュールはタイトにみたいなお題はありつつ、一方で視聴対象年齢を上げる作品への挑戦もしなければならない。だからこそ、いろいろと制約を逆手に取ることを考えました。それならば独自の戦闘空間であるメタフィールドを設定しようとか、連続ドラマとしてキャラクターを複数回にまたがって登場させることで認知を深めようとか。ガルベロスであったり、ノスフェルであったり、ペドレオンであったりといったスペースビーストたちは、未だに忘れられてはいないと思うので、そこは怪獣スターシステムとしても成立していたかなと。
――今回の取材にあたって、久々に『ネクサス』をイッキ見させていただいたんですが、自分の記憶以上に西条凪副隊長がツンケンしていて驚いたんです。でも実際、『ネクサス』だけが突出してギスギスしてる番組という印象はなかったんですよね。
当時のエンタメ全体の流れとして、そういう感じがあったのかなって気もします。予定調和だけを描かないストーリーは、アニメ作品であれば気にならないのに生身の人間が演じるとまた印象が異なる場合もあります。副隊長も「凪」という名が表すように、最初と最後の印象が異なる役柄なので、演じてくれた佐藤康恵さんも大変だったと思います。
――やっぱり大人のファンを獲得しようということになると、どうしてもシリアスな方向に舵を切りがちだったというか、当時としてはそれ以外の選択肢がなかった気がするんです。今となっては明るく楽しい雰囲気の作品も増えてきてますが。
そうですよね。『ULTRAMAN』は、まさにそういう大人向きの部分を強く出そうとしていた作品でした。20世紀末から21世紀へ、終末思想から混沌の中に未来を見出そうとする時代への過渡期、でもそういう時代だからこそ正義を語るというんですかね。きちんとウルトラマンについて考えたものを送り出したいという気持ちが、小中(和哉)監督と長谷川(圭一)さんと鈴木プロデューサーら作り手の中にあったことは確かだと思います。あと、当時の流行の話をすると、Jホラーのブームもありましたね。『リング』や『呪怨』が、世界的に評価を受けてハリウッドでリメイクされていた時代です。円谷プロもミステリー路線は『ウルトラQ』の頃から手掛けていました。『怪奇大作戦』もありますしね。
――そういう意味では、ホラーテイストの怪獣というアプローチも、それほど突飛なものではなかったというか。
ええ。でもJホラー作品も出てくるまでが一番怖くて、そういう部分は相性がよかったと思うのですが、通常の特撮作品でもいざ怪獣が出てくると落差が出る、みたいなところもあったりするじゃないですか。だから、そこは演出の積み重ねでいつもよりは怖く見えたらいいなと思ってはいたのですが、あまりに「怖かった!」と言われると、「そんなに怖かったですか、申し訳ありません!」みたいな気持ちにもなります(笑)。一方で未就学の子供たちは、意外とすんなり観てくれてたりしていて……もちろん、すごく怖かった子もいたかもしれないけど、わりとウルトラマンの活躍ばかり覚えていて、のちに大きくなってから観返したとき、「こんな重厚な話だったんだ……」って驚いたという話もよく聞きますね。まあ、それはそれでひとつのプレゼントというか、ウルトラマンシリーズの醍醐味のひとつではあるのかなと。
――第1話のペドレオンは、巨大化形態のグロースこそスーツによる撮影ですが、クラインとフリーゲンは3DCGのキャラクターになっていて、まさに歴史の転換点にある作品だったなと。
なかなか野心的なことをやっていたんですよね。CGでいうとクロムチェスターのアビロックミサイル一斉発射といった、「板野サーカス」カットの導入にも挑戦しました。当時、日本人の想像力から生み出される作品が、世界にも広く受け入れ始められていましたよね。ジャパニメーションがあって、Jホラーがあって、その次に来るのは特撮だろうという想いが強くあったんですよ。だからアニメの持つアクションの要素や、Jホラーの持つミステリアスな要素を特撮に導入して、日本だけでなく世界と戦える作品を目指したかった。それで音楽には川井憲次さんをお招きしましたし、CGIモーションディレクターとして板野一郎さんをお呼びしたんです。アニメの世界で「板野サーカス」と称されるスペシャルカットを手掛けられた板野さんに、3DCGアクションのディレクションをしていただくことで『ネクサス』ならではのルック、ビジュアルインパクトを作れないかと。かつての円谷プロ作品でも『(恐竜探険隊)ボーンフリー』や『(恐竜大戦争)アイゼンボーグ』では、キャラクターを2Dアニメーションで描き、逆に手描きだと大変なメカはミニチュアワークで表現するという試みをやっていたじゃないですか。『(プロレスの星)アステカイザー』も、カイザーインしてからのアクションシーンをアニメーションにしていましたよね。
――今となってはプロレスバトルこそ実写でやるべきだったのでは?と思ったりもしますが、そういう歪さがあったからこそ未だに語り継がれてるようなところもありますね。
でも、そのスペシャルカットに、のちのアニメブームを牽引するようなスーパーアニメーターやクリエイターたちが本領を発揮していたら、また違ったかたちで語り継がれていただろうとも思うんですよ。『ネクサス』でも板野さんにご参加頂き、アニメ的なアクションやケレン味あるカットの導入に挑戦しましたし、後に企画協力として参加した『(SSSS.)GRIDMAN』では、特撮好きの雨宮(哲)監督が、キャラクターは2Dで、メカアクションを3DCGにして特撮の要素を取り入れたアニメーション作品を作り上げて好評を得ました。今はミニチュア特撮の要素が3DCGに置き換わり、そこにアニメ的なアクションも付加して違和感のない表現ができる時代になったわけです。そういう意味ではアニメと特撮を融合させるという『ボーンフリー』などの企画コンセプトも、先見の明があったんですよ。『ネクサス』でも、特撮の新しいスタンダードを作りたいと思っていた部分がありました。当時はミニチュアを使っているシーンとCGの併用でしたが、ストライクフォーメーションの合体シーンのような繰り返し使われるバンクカットだけでなく、例えばEpisode.24「英雄‐ヒーロー‐」のラストバトルの一連なども、アニメの持つタイミングやスピード感をCGに置き換えて再現するだけでなく、本編・特撮・CGが融合したカタルシスを得るシーンにすべく、板野さんに本編と特撮とCGを分けない一連の画コンテを描いてもらったりしていました。
「諦めるな!」の精神
――今でこそ再評価の機運が高まっている『ネクサス』ですが、当時はなかなか具体的な成果に結びつかず、忸怩たるものがあったと思うのですが。
円谷プロ作品はあとから時代が追いついてくるような先見性があるものも多いのですが、やっぱり初動でも成果を得る必要がありますから、様々な要素で苦戦を強いられたということでは、作品に真剣に取り組んでくれていたスタッフやキャストたちの現場に苦労をかけてしまったなという想いはありますね。じゃあ、プロデューサーとして彼らに何が返せるか、何で報いるかといったら、それは正当な作品への評価しかないと思うんですよ。放送が短縮になったからといって「謎が回収できなかったのは話数が短くなったからだよ」と投げっぱなしで終わらせることはできないですし、物語を破錠させることなく終盤の展開で「盛り上がったよね、最後まで観たらいい話だったよね」というところに着地させるのがプロデューサーとしての責務だと思ってました。だから最後まで観ていただければ、ちゃんとカタルシスのあるシリーズだと言ってもらえる作品にすることを諦めませんでしたし、そういう意味でも、「最終回がよかった!」と言ってもらえるのは、作り手としては最高の名誉ですね。
――当時のインタビューで脚本家の太田愛さんが語っておられましたが、第三の適能者が憐であることをはじめ、いわゆる姫矢編以降の展開は何も決まってなかったそうですね。ガラッと明るい雰囲気に変わることぐらいは考えられてたそうですが。
ええ。先ほども話したようにラストの展開こそ決めていましたが、ここはガラッと明るい雰囲気に変わるという計画的路線変更枠でしたね(笑)。シリーズ構成の長谷川さんも、敢えて全貌を知らない太田さんに考えてもらい、自分以外の才能が入ることによる化学変化を期待していた部分はあったと思います。ちなみに以前の太田さんは『ダイナ』の「少年宇宙人」をはじめとするジュブナイルものをたくさん書かれていたので、自分たちとしても少年モノがいいよねとは考えていましたが、「少年モノをお願いします!」というふうに決め込んで振ったりはしていなかったですね。自由な発想をしてもらいたかったので。
――たとえば太田さんが千樹憐という新キャラクターではなく、吉良沢だったり、あるいはナイトレイダーの誰かを新たな適能者として描きたいと仰られた場合、渋谷さんたちはGOサインを出したんでしょうか?
かもしれないですね。もちろん、それは20年前の自分に聞いてみないと分からない部分もありますけど、太田さんのことはとても信頼していましたので。現にプロメテウス・プロジェクトという設定は太田さんが作ってくれたもので、吉良沢もプロメテの子として憐との過去が設定されたことで深みが増し、双方のキャラクターが補完されました。
――初の連続ドラマ形式ということもあって、ホン打ちも気合が入っていたとか。
撮影が始まってからは難しくなりましたが、朝から晩まで全ライター、全監督が集まって、「こういう引きにするならば、次はこういう展開だよね」みたいな感じで打ち合わせも連続してやっていましたね。一話完結形式だとキャラクターの感情が毎回リセットされてしまうこともありますけど、『ネクサス』に関しては「こんなに辛い試練にぶち当たったら、とても翌週では立ち直れてないだろう」というように議論を重ねて、キャラクターの心情に寄り添いながら、その成長を丹念に描いていました。連続モノの醍醐味ではありますが、展開がもどかしいとか、観ていて辛いときもあったと思われる方もいらっしゃったと思うので、なかなかバランスが難しいところですけどね。たとえば『あしたのジョー』を読んでいても、力石戦のあとのジョーって、なかなか立ち直れなかったじゃないですか。地方のドサ回り、草拳闘にまで身を落として、それからやっと復帰しても相手の顔(テンプル)を打てなくなってしまう。当時、アニメ化も決まっていて、まだ力石と戦いを続けて欲しいという話もあったそうなんですが、梶原一騎先生とちばてつや先生はそれを拒否されて、あの壮絶な死闘を描ききりました。もちろん、その後のジョーだって、そんな簡単に立ち直れるはずはないとジョーとともに苦しみながら取り組まれていたんだろうなと思いますね。読者や周囲のことを考えたら、すぐに復活すべきなのかもしれないけど、作品を真剣に描ききろうとなったらそうとばかりもいかない。その想いは自分もモノ作りをするようになって理解できるようになりました。
――『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦!ベリアル銀河帝国』のノアや『ウルトラマンX』第20話におけるネクサスの扱いを見るに、作り手の『ネクサス』に対する格別の思い入れの深さみたいなものを感じるんですが、それも連続ドラマだったからこそなんですかね。
そうですね。ネクサスを「絆」や「諦めるな」といったメッセージを象徴するキャラクターに昇華できたのも、連続ドラマ形式を貫いたからだと思います。それに現場も大変でしたしね。逆風の中にあっても初志貫徹するぞって、逆に結束できた部分もあったりしましたし、スタッフ・キャストが一丸となって一緒に辛い時期を乗り越えた……まさに同じ釜の飯を食った戦友たちという感覚があります。それはバンダイさんにしてもそうですよ。「合体するメカにしましょう!」と我々の企画に賛同してくれて。
――「絆」というテーマからの発想で、ストライクチェスターは合体メカだったんですか!
こちらも絆をテーマにする作品で合体メカを活かしたいと思っていましたので、打ち合わせを経て企画にすり合わせてもらえたのはありがたかったですね。最初はジェットビートルみたいな形だったデザイン案が、作品のテイストに合わせて、リアル寄りのデザインにスライドしていったんです。チェスターって、ミリタリズムに寄りすぎてはいないものの、でもちゃんとSFメカじゃないですか。デザインもですが、カラーリングにもこだわりました。たとえばカーキ色のMA-1を着たら完全にミリタリーテイストになるけれど、エアフォースブルーだと地味すぎず、メカに反映してもSF感もあって馴染むというか。青は赤に次いで男の子の好きな色だし、それでナイトレイダーの全体的な色味を青にしたんです。チェスターに関しては、横須賀線みたいな色にしたいという話をしましたが、それならばナイトレイダーの部隊マークは白の単色でデザインするといいアクセントになりますよといったやり取りもありました。世界観的に派手なマークは似合わないですし、玩具的にも単色であればデカールを貼るのではなく、タンポ印刷で部隊マークが入れられると。そういう作品と玩具展開の両面を踏まえてのご提案はとてもありがたかったですね。あれから20年の月日が流れましたが、新たにプレミアムバンダイからハイパーストライクチャスター(ウルトライドクロニクル ハイパーストライクチェスター)も発売されますし、今回のアルティメットルミナスにおけるネクサスの展開もとてもありがたいことだと思っています。
――放送終了後のインタビューを読み返してみると、皆さんどこか清々しい感じで振り返られてる印象で、やっぱりそこは初志貫徹することができたということが大きかったんですかね。
「それでもノアは出すぞ!」みたいな気持ちで臨んでいましたからね。まあ、そこの情報は開示してなかったわけだから、別に文句は出なかったと思うんですけど(笑)、でもやるんだよと。最終的な適能者を孤門にするっていうのもそうで、そのためのドラマだったんだから、これをやらないでどうする!?という感覚でした。で、最後まで観て「なるほど!」と思ってもらえれば、作品を通して伝えたかった想いも理解してもらえるだろうと。これが中途半端に終わってしまったら、「最初のコンセプトはよかったかもしれないけどね……」とか、そのくらいの評価になって、とても長く語り継がれるような作品にはならないと思ったんですね。実際、過去にそういう惜しい作品を視聴者として観ていて「なんで変えるかなぁ?」と思っていた人間としては、次の世代にそう思わせないよう、テーマが変わってしまうものは絶対に作りたくなかった。僕はよく“路線変更は視聴者への裏切り”という話をするんですが、発言の趣旨としてはそういうことです。さっきイッキ見していただいたという話がありましたけど、今はそれができる。ドラマ部分や謎解きの面白さで年長の視聴者も楽しめる連続モノにしていたので、配信などで続けて観ると余計に面白く感じられたり、伏線がよく分かったりするような側面もあると思うんですよ。視聴層も多岐に渡るようになり、『シン・ウルトラマン』の公開を経て、『ULTRAMAN』も再評価を受けています。20年の月日が経って、ようやくそういう時代が来たんだなと嬉しく感じていますね。アルティメットルミナスでネクサスやノア、ザギが出ることもとても嬉しいです。ちゃんと今でも好きだと言ってくれるファンの人たちがいて、『ネクサス』も人気投票系の企画などではベスト10入りを果たしたりしているわけじゃないですか。それもとても嬉しいことですし、あのとき、本当に諦めずに頑張ってよかったなと思いますね。
――ネクサス、ノア、ザ・ネクストは、それぞれどういった流れでデザインが成立していったんでしょうか?
最初に企画としてスタートしたのは映画の『ULTRAMAN』なので、まずザ・ネクストの外骨格のようなアンファンスやジュネッスからデザインが決まりまして、そこからテレビシリーズのデザイン作業に移っていきました。ノアも含めてデザインは丸山(浩)さんなのですが、ネクサスはスタイリッシュなスタイルにということで、兜や陣羽織を羽織ったような和のテイストもある独特のシルエットに洗練されたものになりました。エナジーコアは、それぞれ統一した印象を持たせるための意匠ですね。同族なのかな?というミスリードになればとも考えていました。ノアに関しては、ザ・ネクストが光として落ちてきたときの本当の姿なんじゃないか?という発想から、最初はもっと羽衣をまとったようなデザイン画もあったんですよ。でもイベントやグラビアで稼働してもらうことを考えると、ヒロイックな印象の光の巨人にしたいよねということで、現在のノア・イージスの意匠を持つデザインに落ち着きました。あとは、イベント先行ということで映像では嫌がれるけど、実際に見るといいよね!みたいな要素も積極的に取り入れていこうということで、アップ用のノアは塗装による銀ではなくて、全身レフ板のようなメタリックな質感のものでした。ダーグザギに関しては、やっぱりプレパブリシティ展開にはノアに対抗する敵キャラクターが欲しいという声もあり、分かりやすいアイコンとしてノアの色違いのデザインという案に落ち着きました。『ウルトラマンコスモス』のときも、カオスウルトラマンがいましたが、ザギに関してもデザインとカラーリングと設定の三要素でキャラクターを立てたいという想いがあったんです。ノアとザギは菊地(雄一)監督の演出による最終回の激闘が何よりもよかったですね。
――なるほど。今回のアルティメットルミナスは如何ですか?
すごいですね。エナジーコアと目が光ってる! 目や胸の光が常に輝いているのはウルトラマンならではの特徴ですが、それをこのサイズ感で再現しているのは素晴らしいですし、ポージングといい、本当にもう今にも動き出しそうな感じで、ミニチュアセットを組みたくなってしまいますね(笑)。ノアだけでなく、ザギも素晴らしいなぁ。ザギは、(岩田)栄慶くんが演じていたんですよね。栄慶くんは、当時からとても勉強熱心でした。プロデューサーとして現場に行くと、「このあと、溝呂木やダークメフィストはどうなるんですか!?」みたいなことをよく訊かれましたよ。スーツアクターは、監督や殺陣師の指示通りに動くだけではなく、きちんとキャラクターの内面を理解して、それを演技に活かしたいのだと。そんな彼の貪欲な姿勢まで思い出してしまいました。

――実はザ・ネクストも商品化が決定しているんです。感想をお願いできますか?
なんと!それは感慨深いですね…。ウルトラマン ザ・ネクストと、ウルトラマンネクサス、そしてウルトラマンノアは、同一のキャラクターであると同時に、またそれぞれ独自の活躍を繰り広げてきた存在です。それらが発光する精密なフィギュアとなって並び立たせることができる日が来るとは、感無量です。「光は絆」ということで、是非手に取ってそれぞれの光に想いを馳せていただければうれしく思います。ありがとうございました。

- ■渋谷浩康
- 1969年生まれ 神奈川県茅ケ崎市出身
1992年円谷プロダクション入社。『電光超人グリッドマン』(93)の製作進行や『ウルトラマンゼアス』(96)等のアシスタントプロデューサーを経て、『ウルトラマンコスモス』(01)以降、『ウルトラマンネクサス』(04)『ウルトラマンメビウス』(06)『ウルトラギャラクシー大怪獣バトル』(07)等のTVシリーズ作品でプロデューサーを歴任。近年は『グリッドマンユニバース』(23)の企画協力や『ウルトラマンアーク』(24)の設定監修等、企画協力や設定監修の立場で多くの円谷プロ作品に携わっている。
■聞き手: ガイガン山崎